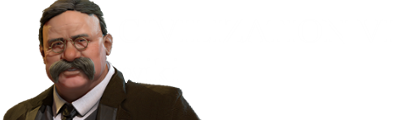
���Ĥϡ��ԻԤ���Ǥ�����뤳�ȤǸ��̤�ȯ�����롣
��Ǥ���ؼ��塢������ε������в��ʥ����ॹ�ԡ��ɤ˴ؤ�餺����ˤ���Ǥ���롣
��Ǥ���ԻԤ��ѹ�����ݤ�Ʊ�������Υ�������Ȥ�ɬ�פˤʤ롣
���Ĥ���Ǥ��Ȥʤä��ԻԤϡ����������ä�+8�Υܡ��ʥ��������롣
�������Ǥ��ؼ��塢��Ǥ��λ���Υ�������Ȼ�������ͭ���Ǥ��롣
�������Ǥ����λ����ȡ����Ĥ��Ȥ˰ۤʤ�ܡ��ʥ��������롣
���Ĥξι��������뤴�Ȥˡ��������Ѥ����ʤ����뤫�Τ����줫�����֤��Ȥ��Ǥ��롣
���Ĥξι�γ�����ˡ�ϡ��Ҳ����٥ĥ�ο�Ÿ�Τۤ�������ʣ����߶��Ȥ��η�¤ʪ�η��ߡ��仺���̾����פμ��Ϸ��ߤʤɡ�
���ĤȤ��ƺ��ѤǤ���Τϳ�ʸ�����̤ǰʲ���7�͡�GS�Ǥϥ��쥤�ޥ�1��(ˡ����)����Ƴ�ԤǤ������8�ͤȤʤꡢ���������Ĥ�ǽ�Ϥ��Ѳ����Ƥ���(�ʲ���GS���Ǥ�����)��
�ʤ���NFP����̩��ҡץ⡼�ɤ����ĤˤĤ��Ƥ�������ι��ܤ�
�����ʸ��̤Υ��������������ä˸�������������¿���١�����
��˷����Ϥζ�������Ū�Ȥ������ġ�
RaF�Ǥ���̯�������ǽ�Ϥ��ФäƤ��ꡢ�ޥ��ʥ��������˱�����������Ѥ���ʤ��ä����ᤫ��GS �ǤϷ���������������������ǽ�Ϥ��ɲä��줿��
�ʤ���̵�������ʵߺ����֤Τ��ᡢ1�Ĥξ��ʤ���˥����ϥ���2�Ĥθ��̤�Ʊ���˴ޤޤ�Ƥ��롣
���ѥܡ��ʥ����������ϡ��ԻԤ��ɱ��Ϥ����ǽ�ϡ�
���̤Ρּ�����ˤ��![]() ��Ʈ��+5�פȤ��Կ���ʼ�ľ����Ʈ��˥åȤ�
��Ʈ��+5�פȤ��Կ���ʼ�ľ����Ʈ��˥åȤ�![]() ��Ʈ��+5�ʤΤǴ���Ū�ˤ��ɱҸ�����¾���ɱҸ��̤ȹ�碌��Ф��ʤ��ԻԤ���Ȥ���ˤ����ʤ��������
��Ʈ��+5�ʤΤǴ���Ū�ˤ��ɱҸ�����¾���ɱҸ��̤ȹ�碌��Ф��ʤ��ԻԤ���Ȥ���ˤ����ʤ��������
�ʤ�����3������Ǵ�������פȤϡ���Ǥ�ޤ�3������ݤ���פȤ�����̣�ʤΤ����ա�
����Ū�ش����ϡ��ԻԤ��ɱ��Ϥ������������ǽ�ϡ�
��Ȥ�Ȥθ��̤Ǥ�����ɱ�![]() ��Ʈ��+5�פ��θ����ȡ����������ԻԤ��ɱҤ˻Ȥ����ɤ���������GS���ɲä��줿�֥��������������+4�פ��θ����ȡ���������������䤹�����Ϥ��ԻԤ����֤���Τ��ɤ�����������ɽ���Ǥϡ�¾�ԻԤ��Ф��פȤ��뤬�ºݤ���Ǥ�����ԻԼ��Τˤ���̤����롣
��Ʈ��+5�פ��θ����ȡ����������ԻԤ��ɱҤ˻Ȥ����ɤ���������GS���ɲä��줿�֥��������������+4�פ��θ����ȡ���������������䤹�����Ϥ��ԻԤ����֤���Τ��ɤ�����������ɽ���Ǥϡ�¾�ԻԤ��Ф��פȤ��뤬�ºݤ���Ǥ�����ԻԼ��Τˤ���̤����롣
�ɱ�ʼ���ϡ��ԻԤ��ɱ��ϵڤӻ���������ǽ�ϡ�
���ԻԤ���Ϥ���ʤ��פȤ�����̯��ǽ�Ϥ����ʤ��ä�����GS�Ǥϡ֥����Ȥ���ά��+1�פ��ä�ä�������Υ쥢��ά���Τ���ԻԤ˾�����Ȥ�����������
�ƴ��ϡ��Ի�ˤ��ڤӷ�������������˥åȤ�����ǽ�ϡ�
���ԻԱ�ֹ�����+1�פ���Ϥꥷ��ܤ��������ᡢGS �ǡ֥�˥åȤ�̵����٥륢�åספ��ɲä��줿�������ò��ԻԤǻȤ��ʤ�Ƽ������ˤ��������Ȥ߹�碌��ʤꤷ�ơ��������®���륮�ߥå�������ȳ褭�롣�ʤ�̵����٥륢�åפϳ����䥹�ѥ��ˤ�Ŭ�Ѥ���롣�ä˥��ѥ��ϥ�٥륢�åפβ��ä������١������¤ꤳ���ԻԤǷ��������������������ȥ�̤Ρ�����ͷ����פȤϽ�ʣ���ʤ���
�ɶ����������ȶ���ٻ����ϡ���ʼ��˴ؤ���ǽ�ϡ�
��˳�ʼ��ν���®�٤ι�®���ȳ�ʼ����Ф����ɱ��Ϥ���夲���뤬������ʳ��ˤϸ��̤��ʤ��ΤǴ���Ū�ˤϼ������ʤ��Ƥ⤤����
����ԻԹ�ȤȤδط�������Ū�Ȥ������ġ�
ͣ�졢�ԻԹ�Ȥ��ɸ��Ǥ������Ĥǡ��ԻԹ�ȤȤδط����Ǥ����ˡ������ԻԹ�Ȥ����͡��ʲ��ä������롣�ä˽����ܡ��ʥ������������ԻԹ�Ȥ��˭�٤��ԻԹ�Ȥ��֤��Ƥ����С�����θ��̤���ԤǤ��롣
�ɸ�����ԻԹ�Ȥ�����ˤʤ���Ƥ��Ф���뤿�ᡢ�����֤�ɬ�ס���������ԻԹ�Ȥˤ��ɸ��Ǥ������ä˥��ޥˤ�ǽ�Ϥǽ����ˤʤäƤ��������礭��![]() ��ɽ�Ĥο�������Υ����Ƥ��ޤ���
��ɽ�Ĥο�������Υ����Ƥ��ޤ���
����̩��ҡפ���ӡֱ�ͺ������ץ⡼�ɤǤ�![]() ��ɽ���ɸ�������ˤ���Ҥ���ӱ�ͺ��ȯ���Ǥ���������ޥˤ�ǽ�Ϥˤ���Τ�Ŭ�Ѥ���롣����ˤ���̾�⡼�ɤ�������٤��⤯�ʤä��ȸ����롣
��ɽ���ɸ�������ˤ���Ҥ���ӱ�ͺ��ȯ���Ǥ���������ޥˤ�ǽ�Ϥˤ���Τ�Ŭ�Ѥ���롣����ˤ���̾�⡼�ɤ�������٤��⤯�ʤä��ȸ����롣
�ʤ��ԻԹ�Ȥ��ò����������Ǥ��뤬����ˡ����ԻԤ����֤Ǥ��뤳�Ȥ�˺��뤳�Ȥ����롣�����ơ��̤�饦�����ǥץ쥤����ݤ�������������Ƽ��ԻԤ�ԵӤ������Υȿ��Ľ��ΤdzФ��Ƥ���������
���ѥܡ��ʥ��������ϡ����ޥ˼��Ȥ�![]() ��ɽ��2��ʬ�ˤʤ�ǽ�ϡ�
��ɽ��2��ʬ�ˤʤ�ǽ�ϡ�
���פ�![]() ��ɽ�ĤϽ������Υܡ��ʥ����ߥå����ʾ�ˡ�+1���Ĥ��������ʤ��Τ�
��ɽ�ĤϽ������Υܡ��ʥ����ߥå����ʾ�ˡ�+1���Ĥ��������ʤ��Τ�![]() ��ɽ��+2ʬ��Ư���ϡ�
��ɽ��+2ʬ��Ư���ϡ�![]() ��ɽ��1�Τȥ��ޥˤ��ɸ�����Ф����˽����ˤʤ�롣�ä��ԻԹ�ȤϽ�ν����ˤʤ��٤˻��女���Ȥ�+2���㤨��Τǡ���꤯�Ԥ���
��ɽ��1�Τȥ��ޥˤ��ɸ�����Ф����˽����ˤʤ�롣�ä��ԻԹ�ȤϽ�ν����ˤʤ��٤˻��女���Ȥ�+2���㤨��Τǡ���꤯�Ԥ���![]() ������������䤹���ʤ롣
������������䤹���ʤ롣
�����ϡ�¾ʸ���ԻԤ��������餹ǽ�ϡ�
![]() ��������
��������![]() �����ץ��������Ȥˤ�����������Ϥ��θ���ƾ�꤯�ɸ��Ǥ���С��ԻԤ�Υȿ�����䤹���ʤ��������
�����ץ��������Ȥˤ�����������Ϥ��θ���ƾ�꤯�ɸ��Ǥ���С��ԻԤ�Υȿ�����䤹���ʤ��������
����������������ϡ��ԻԹ�Ȥ���β��ä����䤹ǽ�ϡ�
��ʸ���������Ƥ�����䤦�ݤ�����������![]() ��ɽ�ĥܡ��ʥ��佡���ܡ��ʥ����ߤ����ԻԹ�Ȥȡ��ߤ�������äƤ��ԻԹ�Ȥ�ɬ��������פ��ʤ��Τǡ��ɤ����ͥ�褹�٤����Ϲͤ��褦��
��ɽ�ĥܡ��ʥ��佡���ܡ��ʥ����ߤ����ԻԹ�Ȥȡ��ߤ�������äƤ��ԻԹ�Ȥ�ɬ��������פ��ʤ��Τǡ��ɤ����ͥ�褹�٤����Ϲͤ��褦��
���Ͼ������ϡ���Ǥ�����ԻԤ���ĵ�Ϥ����ǽ�ϡ�
����ɮ�Ԥ�
�ͷ������ϡ��ɸ����Ƥ���![]() ��ɽ�Ĥ�����������ǽ�ϡ�
��ɽ�Ĥ�����������ǽ�ϡ�
����������Τϥ��ޥˤˤ��![]() ��ɽ�ĤΥܡ��ʥ��������
��ɽ�ĤΥܡ��ʥ��������![]() ��ɽ�Ĥο����֥ܥ����˥�פΤ褦��AI��ͥ���٤��⤤�ԻԹ�Ȥν�����ݻ�������˽������롣�ʤ����ԻԹ�Ȥ����Ϥ�
��ɽ�Ĥο����֥ܥ����˥�פΤ褦��AI��ͥ���٤��⤤�ԻԹ�Ȥν�����ݻ�������˽������롣�ʤ����ԻԹ�Ȥ����Ϥ�![]() ��ɽ�Ĥο��ˤ�äƳ��礹�뤿�ᡢ�ؿͷ������٤���������ִ֤˰쵤�����Ϥ��롣���ܤ����ԻԹ�Ȥ��ä���硢���Ϥ�����ˤʤ뤳�Ȥ⤢��Τǥ����ߥˤ����դ�������
��ɽ�Ĥο��ˤ�äƳ��礹�뤿�ᡢ�ؿͷ������٤���������ִ֤˰쵤�����Ϥ��롣���ܤ����ԻԹ�Ȥ��ä���硢���Ϥ�����ˤʤ뤳�Ȥ⤢��Τǥ����ߥˤ����դ�������
��˽����ζ�������Ū�Ȥ������ġ�
�����ץ쥤��ɬ�����ġ��������̤��ĥ�α��˽��椷�Ƥ�����⤢�äƽ����ò��ʳ��ǤϻȤ��ɤ���
��2021ǯ4��ץǤˤƺ��ѥܡ��ʥ����ԻԤ������褴�Ȥ�![]() ������+2�θ��̤��ɲá�
������+2�θ��̤��ɲá�
���ѥܡ��ʥ����ʶ��ϡ���Ǥ�ԻԤν���Ū���Ϥ��ᡢ�ԻԤο����Ϥ����䤹ǽ�ϡ�
����Ū�������ä�ͤ���ȡ��ब�����ԻԤ����Ԥˤ��ơ�![]() ���ԤȤ��̤ν��������ԻԤ�Ω���夲��Τ⤤�����⤷��ʤ���
���ԤȤ��̤ν��������ԻԤ�Ω���夲��Τ⤤�����⤷��ʤ���
�翳�䴱�������μ��ϡ���������κ��������ԻԤ�ͭ�ס�
Ũ������˥åȤ��ʤ�����������ԻԤ��Ԥ������ơ��֤�Ƥ���ˤ��褦��
�ʤ��������μ��Ϸ�����˥åȤ�![]() HP�����������Τǡ����ƥץ쥤�Ǥ�Ȥ����Ȼפ��лȤ��롣
HP�����������Τǡ����ƥץ쥤�Ǥ�Ȥ����Ȼפ��лȤ��롣
���κ��ϡ���Ǥ�����ԻԤ�����Ū���Ϥ�����ʤ��ʤꡢ���ߤ�![]() �����Ϥ�������ǽ�ϡ�
�����Ϥ�������ǽ�ϡ�
����ɮ�Ԥ�
��������ϡ����̤��ɲäξ��ʤ�������ǽ�ϡ�
�۶���ư�Ǥ��ä˶��ϡ��������褬�ܳʲ�������������ʹ��ޤǤˤϳ�����������
���ʤ���ۼ��ϡ�![]() �����ϤǶ�褬�����Ǥ���褦�ˤʤ�ǽ�ϡ�
�����ϤǶ�褬�����Ǥ���褦�ˤʤ�ǽ�ϡ�
�������褬�������![]() �����Ϥ�;͵���ФƤ�������Ѥ��Ƥ⤤�����⤷��ʤ���
�����Ϥ�;͵���ФƤ�������Ѥ��Ƥ⤤�����⤷��ʤ���
���![]() �����Ϥζ�������Ū�Ȥ������ġ�
�����Ϥζ�������Ū�Ȥ������ġ�
���ĺǶ����ġ����פ��齪�פޤ��Ի���Ĺ��ľ�뤹��![]() ������
������![]() �����Ϥ����䤻��Τ��Ի���Ĺ�Ȥ������Ǥ�Ĵ�������¡פ�Ʊ�͡����ˤ�����Ƥ��롣�ޤ�����ĥ������ǽ�Ϥ⤢�ꡢ���פ�
�����Ϥ����䤻��Τ��Ի���Ĺ�Ȥ������Ǥ�Ĵ�������¡פ�Ʊ�͡����ˤ�����Ƥ��롣�ޤ�����ĥ������ǽ�Ϥ⤢�ꡢ���פ�![]() ���ĺ��ѤǤ϶���ԡ֥ԥ�פȤ�������ˤʤ롣
���ĺ��ѤǤ϶���ԡ֥ԥ�פȤ�������ˤʤ롣
���ѥܡ��ʥ��������ϡ���ʪ����ν���ܡ��ʥ������䤹ǽ�ϡ�
���ѥܡ��ʥ�����Ǥ�GS�Ǥ����Ѥ�餺�Ƕ����饹������Ǽ����̤����ƿ��Ӥ�Ǯ�ӱ��Ӥ���Ȳ����С�����Ū�ʽִֻ��Ф�á���Ф��롣
�ʤ������ϥܡ��ʥ���ŷ���ӤΤߤʤΤ����ա������ݸ�ǿ��Ӥ��Ӳ�ǽ�ˤʤ뤬���������(�ޥ��ʥ���̵ͭ�˴ط��ʤ�)Ȳ�Τ��Ƥ�![]() �����Ϥ������ʤ���
�����Ϥ������ʤ���
;������ϡ��ԻԤ�![]() ����Ĺ�ȹ����פdz褭��ǽ�ϡ�
����Ĺ�ȹ����פdz褭��ǽ�ϡ�
��賫ȯ�Ѥ����ԻԤ˾����ơ�����ο����ԻԤ��������ɸ�����С�![]() ������
������![]() �����Ϥ��������Ǥ��롣��Ȥ��Ƹ�ץܡ��ʥ����⤤����ʣ����ߤȳ����Ȥ߹�碌�����
�����Ϥ��������Ǥ��롣��Ȥ��Ƹ�ץܡ��ʥ����⤤����ʣ����ߤȳ����Ȥ߹�碌�����![]() ����+5��
����+5��![]() ������+3������졢¾�ζ��η��ߤǤ�������ä��롣
������+3������졢¾�ζ��η��ߤǤ�������ä��롣
�����ϡ��ԻԤ�![]() ���ˤ�������Ԥ������Ǥ���褦�ˤʤ붯����ǽ�ϡ�
���ˤ�������Ԥ������Ǥ���褦�ˤʤ붯����ǽ�ϡ�
![]() ���餵�ʤ��ʤ�Τ������˥������Ϳ���뤳�Ȥ��ʤ���ˡ�������к������ֿ�̱�ϲ��פȥ��åȤˤ����ԻԤѥष�Ƥ������Ȥ��Ǥ��롣�������פ�
���餵�ʤ��ʤ�Τ������˥������Ϳ���뤳�Ȥ��ʤ���ˡ�������к������ֿ�̱�ϲ��פȥ��åȤˤ����ԻԤѥष�Ƥ������Ȥ��Ǥ��롣�������פ�![]() ��Ŭ�����к��Ȥ��Ƥ����Ƴ���Ժ�����
��Ŭ�����к��Ȥ��Ƥ����Ƴ���Ժ�����![]() ���餹�ƥ��˥å��⤢�롣
���餹�ƥ��˥å��⤢�롣
�¶Ȳ��ϡ������ȯ�Ž����ǽ���夲��ǽ�ϡ�
����ɮ�Ԥ�
�Ǿ����ϡ���˥åȺ����˳ݤ��������ޤ���ǽ�ϡ�
�̾����80%���ʤ�����ǥ�˥åȤ�����Ǥ������������Ǥʤ��������ˤ���̤����롣����Τ���ά�Τߤ����������ȤϿ����֤���
![]() �ϡ�
�ϡ�![]() Ŵ��
Ŵ��![]() ���ФϾ���1��ǥ�˥åȤ�Ф���Τ������Ϥ䥴����ɤϤ��뤬��ά�������ä��Ǥ���褦�ʾ����ʤ�ͭ�Ѥ�Ư����
���ФϾ���1��ǥ�˥åȤ�Ф���Τ������Ϥ䥴����ɤϤ��뤬��ά�������ä��Ǥ���褦�ʾ����ʤ�ͭ�Ѥ�Ư����
��˥åȺ������˾������������ʤΤ�![]() ��ú�ʹߤ��西���������˥åȤΰݻ�����ʬ�ˤϸ��̤��ʤ�������������岽���Ƥ��ޤ����ˤ����ա�
��ú�ʹߤ��西���������˥åȤΰݻ�����ʬ�ˤϸ��̤��ʤ�������������岽���Ƥ��ޤ����ˤ����ա�
��ľ�����ϡ�![]() �����ϥܡ��ʥ����ʣ��������ǽ�ϡ�
�����ϥܡ��ʥ����ʣ��������ǽ�ϡ�
�����ԻԤΤ߶����ԻԤ���ι����ȯ�Ž��![]() ���������ø��̤���ʣ����褦�ˤʤ롣�����ͭ���ϰϤޤ��Ťͤ��
���������ø��̤���ʣ����褦�ˤʤ롣�����ͭ���ϰϤޤ��Ťͤ��![]() �����Ϥʤ���뤳�Ȥ���ǽ�ˤʤ����˶��ϡ�
�����Ϥʤ���뤳�Ȥ���ǽ�ˤʤ����˶��ϡ�
����ʤ�˰ռ���������Ǥ�ʸ���̤��㤤��![]() �����Ϥ�Ф����Ȥ��Ǥ��뤿�ᡢ�ʳؾ�������פʰ仺����ߤ������Ȥ��ˤϤԤä���Ȥ����롣
�����Ϥ�Ф����Ȥ��Ǥ��뤿�ᡢ�ʳؾ�������פʰ仺����ߤ������Ȥ��ˤϤԤä���Ȥ����롣
����Ի���Ĺ����Ū�Ȥ������ġ�
��˼Ĺ�֥ޥ��ʥ��פ�Ʊ�������Ի���Ĺ��¥���Ƥ���뤬����������ä˥�����ˤ���Ի���Ĺ��ô�äƤ���롣
���ѥܡ��ʥ�������ɥޥ������ϡ�ϫƯ�Ԥ�����ǽ�ϡ�
![]() ϫƯ��+1�����Ѥ�餺������ϫƯ�Ԥϥ����Ȥ��ɤ�ɤ�夬�äƤ������ᡢ�������ʾ��+1���礭����
ϫƯ��+1�����Ѥ�餺������ϫƯ�Ԥϥ����Ȥ��ɤ�ɤ�夬�äƤ������ᡢ�������ʾ��+1���礭����
�ԻԷײ�Ѱ��ϡ������ߤ�����Ƥ����ǽ�ϡ�
��������![]() ������+20%�Ϥ���ʤ�˹⤯���ä˽��פ俷���ԻԤζ����ߤ�������Τ��Ի���Ĺ��¥�ʤ��Ƥ���롣���������Ǥ���Ф����Τ��ѿ�ϩ����ࡢ���ϡ��̤Ƥˤϱ��������Ϥη��ߤǤ�ͭ����
������+20%�Ϥ���ʤ�˹⤯���ä˽��פ俷���ԻԤζ����ߤ�������Τ��Ի���Ĺ��¥�ʤ��Ƥ���롣���������Ǥ���Ф����Τ��ѿ�ϩ����ࡢ���ϡ��̤Ƥˤϱ��������Ϥη��ߤǤ�ͭ����
�����Ǻ��ϡ��ҳ��ˤ���ﳲ��ڸ�����ǽ�ϡ�
�ִĶ����̤ˤ������������ʤ��פȤϡ��ּ����ҳ����˲�����ʤ��פȤ�����̣���л���˽����ζ���ԻԤʤ�ͭ�ס��ʤ������仺�ˤ��ҳ��ˤ�ͭ���ʤ�����![]() ���θ������ɤ��ʤ��ˡ�
���θ������ɤ��ʤ��ˡ�
���ƻ�ϡ�������ʳ��ζ�褫��ܡ��ʥ���������ǽ�ϡ�
�ѿ�ϩ�����ࡢ����������Ϥ����ɲä�![]() �����
�����![]() ��Ŭ���Υܡ��ʥ����������ΤΡ����Υ����뤬���äƳ褭����ܿ����ȡ٤����������Ǻ��Ѥ���ˤϳ��ߤ���ʤ��Τ��ͥå���
��Ŭ���Υܡ��ʥ����������ΤΡ����Υ����뤬���äƳ褭����ܿ����ȡ٤����������Ǻ��Ѥ���ˤϳ��ߤ���ʤ��Τ��ͥå���![]() �������������Ω�ƤƤʤ�
�������������Ω�ƤƤʤ�![]() ������ʤ����̤⾯�ʤ����ᡢ���̤���ͳ���ʤ��¤�¾�ξι��ͥ�褷�������褤��
������ʤ����̤⾯�ʤ����ᡢ���̤���ͳ���ʤ��¤�¾�ξι��ͥ�褷�������褤��
�ܿ��������������ȸ���ϡ����줾�����ԻԤ���Ĺ���ԻԤ�![]() ��Ŭ����
��Ŭ����![]() �Ѹ��Ϥ����Ƥ�����ͭ���������߲�ǽ�ˤʤ�ǽ�ϡ�
�Ѹ��Ϥ����Ƥ�����ͭ���������߲�ǽ�ˤʤ�ǽ�ϡ�
ϫƯ�Ԥ�ɬ�פˤʤ뤿�����������������ޤ��ԻԤˤ����β������Ȥ߹����Ф���ʤ뻺�Ф���夲����ǽ�ˤʤ롣
GS�Ǥ�![]() ���ġ��¡פ��ںߤ����ԻԤϸ�ͭ�����λ����̤�������褦�ˤʤä�����ʸ�����Τζ���¤������Ϸ�����������ä��顢����ԻԤ��Ѹ��ԻԤǤ�ä��ꤷ�Ƥ�餪����
���ġ��¡פ��ںߤ����ԻԤϸ�ͭ�����λ����̤�������褦�ˤʤä�����ʸ�����Τζ���¤������Ϸ�����������ä��顢����ԻԤ��Ѹ��ԻԤǤ�ä��ꤷ�Ƥ�餪����
���![]() �ʳ��Ϥ�
�ʳ��Ϥ�![]() ʸ���Ϥζ�����οͤ�Ͷ�פ���Ū�Ȥ������ġ�
ʸ���Ϥζ�����οͤ�Ͷ�פ���Ū�Ȥ������ġ�
GS�ǤϺ��ѥܡ��ʥ��μ��β��Ȱ������������������������������졢���פ��鰵��Ū�Ȥ⤤�������̤�![]() �ʳ��Ϥ�
�ʳ��Ϥ�![]() ʸ���ϤФǤ���褦�ˤʤä�������Ǻ�����ԻԤ���������Τϴ���ϩ���ȸ����롣
ʸ���ϤФǤ���褦�ˤʤä�������Ǻ�����ԻԤ���������Τϴ���ϩ���ȸ����롣
�Ż��ˤ����Ǥ�Ϥ��ʤ���˼�ˤʤ�Τǡ���ĵ�ѤΥ��ѥ��ξ����˺�줺�ˡ�
���ѥܡ��ʥ����ʽ��ϡ���Ǥ�ԻԤ�![]() �ʳ��Ϥ�
�ʳ��Ϥ�![]() ʸ���Ϥ�֡����Ȥ���ǽ�ϡ�
ʸ���Ϥ�֡����Ȥ���ǽ�ϡ�
����ɮ�Ԥ�
�������������ϡ���Ǥ�ԻԤ�![]() ���ˤ�ä�
���ˤ�ä�![]() �ʳ��Ϥ�
�ʳ��Ϥ�![]() ʸ���Ϥλ����̤����䤷�Ƥ���뤫�ʤ궯�Ϥ�ǽ�ϡ�
ʸ���Ϥλ����̤����䤷�Ƥ���뤫�ʤ궯�Ϥ�ǽ�ϡ�
����Τ������ǽ��פ˥����ѥ����칭�줬̵���Ƥ�Ѥ�Ҳ����٤�ʤ�뤳�Ȥ��Ǥ���Τǡ��⤤��![]() �����Ϥ���Ԥ�ϫƯ�Ԥ˲�褦�ˤʤä���
�����Ϥ���Ԥ�ϫƯ�Ԥ˲�褦�ˤʤä���
�������ϡ���Ǥ�ԻԤ�![]() �οͥݥ���Ȼ��Ф�����ǽ�ϡ�
�οͥݥ���Ȼ��Ф�����ǽ�ϡ�
�仺�ˤ���̤�Ŭ�Ѥ����Τǡ�![]() �οͥݥ���ȤФ���仺����ξ�����˷��Ƥ�Ȥ褤(�ʤ��������仺��ĥ��ð��ˤ�Ŭ�Ѥ���ʤ�)��
�οͥݥ���ȤФ���仺����ξ�����˷��Ƥ�Ȥ褤(�ʤ��������仺��ĥ��ð��ˤ�Ŭ�Ѥ���ʤ�)��
�طݰ������賫ȯ�����ϡ����줾��ʸ���������ʳؾ����ò��ʤΤǤ���ϩ���ʤ顣
�طݰ��θ��̤ϡ�![]() �������оݳ��Ǥ��뤳�Ȥ����ա�ʸ�����������ξ�硢�ԥ�Τ����ԻԤˤϹ���ʪ�ۤǤϤʤ����Ѵۤ���Ƥ褦��
�������оݳ��Ǥ��뤳�Ȥ����ա�ʸ�����������ξ�硢�ԥ�Τ����ԻԤˤϹ���ʪ�ۤǤϤʤ����Ѵۤ���Ƥ褦��
���![]() ������ɤζ�������Ū�Ȥ������ġ�
������ɤζ�������Ū�Ȥ������ġ�
![]() ������ɤ����߽Ф��Τ�Ĺ���Ƥ���Τǡ����ԻԤ���Ǥ�������
������ɤ����߽Ф��Τ�Ĺ���Ƥ���Τǡ����ԻԤ���Ǥ�������![]() ������ɤǤϺ���ʤ��ʤ��������
������ɤǤϺ���ʤ��ʤ��������
GS��ʸ������Ŭ�����������̤���������뤫��![]() ������ɤ����߽Ф���褦�ˤʤä���
������ɤ����߽Ф���褦�ˤʤä���
���ѥܡ��ʥ������ϼ����ϡ���Ǥ�ԻԤ����ڳ�ĥ����������к��Ϥ����ǽ�ϡ�
�ܡ��ʥ��Ρֿ��������������ޤ�פ����Ū��ɽ������ȡ��֥������ĥ®��+20%�פȤʤ롣�ޤ���¾ʸ�������褿![]() ���ϩ1�ĤˤĤ�
���ϩ1�ĤˤĤ�![]() �������+3�ȹ�碌��ȡ������פζ���Ȥ��Ƥϰ����ʤ���
�������+3�ȹ�碌��ȡ������פζ���Ȥ��Ƥϰ����ʤ���
��Ĺ���������ϡ������ԻԤ�![]() ������ɻ��Ф����䤹ǽ�ϡ�
������ɻ��Ф����䤹ǽ�ϡ�
���ܥܡ��ʥ���¿���ԻԤ�![]() ����¿���ԻԤ��ɸ�����С����Ф餯
����¿���ԻԤ��ɸ�����С����Ф餯![]() ������ɤˤϺ���ʤ���������
������ɤˤϺ���ʤ���������
��Ĺ�ˤ��������ܥܡ��ʥ�2�ܡʶ���Ū�ˤ�+100%�ˤϡ�¤���꤬�����![]() �����Ϥ��ܤˤʤ롣�⤤���ܥܡ��ʥ�����Ĺ��������ԻԤˤϥ쥤�ʤ�ͥ��Ū�����֤�������
�����Ϥ��ܤˤʤ롣�⤤���ܥܡ��ʥ�����Ĺ��������ԻԤˤϥ쥤�ʤ�ͥ��Ū�����֤�������
����ˡ���̩��ҥ⡼�ɤǤϥߥͥ��������Ρֲ������ʪ�ˡפ�![]() ʸ���ϥܡ��ʥ���徺���롣
ʸ���ϥܡ��ʥ���徺���롣
���Ӵ����ϡ�ʸ������������Ŭ�����⤤ǽ�ϡ�
��̤��ȯ�Υ�����פ�ɽ������Ƥ��뤬�����ߤ����ߤ���Ƥ��ʤ���ħ�ʿ���Ǯ�ӱ��Ӥ��������ʤɡˤ�ͭ�륿�����ؤ��Ƥ��롣
�ܡ��ʥ�����ά�����ϡ���ħ�ǤϤʤ��ʤΤǡ���ħ��̵�����������ͯ�����Ƥ���ʤ鿴�֤��ʤ��������褦��
�����ι��������ԻԤ���Ǥ�������![]() ����������⤯���������ĥ��Ǥ��롣
����������⤯���������ĥ��Ǥ��롣
��Ω������ߤ��ͤᡢ���������ɥ���Ȥ���Ω���褦��������ħ��̵���������Ӥ���ȸ��̤��Ф롣
���ξ��ϻ��٤ϸ��̤ʤ����л��ϸ��̤��ꡣ
���ԡ������äθ��̤Ϥ�Ȥ�Ȥ���ޥ��ʥ����ä���櫓�ǤϤʤ����Ȥ����ա�Ǯ�ӱ��ӡ������������������ܥ�����ؤΥ��ԡ�����̤Ϥ�Ȥ�Ȥ�-1���껦���ơ�0�ˤʤ롣
����������ϡ�![]() ������ɤ�ί�ޤäƤ������˼����ɤ�ǽ�ϡ�
������ɤ�ί�ޤäƤ������˼����ɤ�ǽ�ϡ�
![]() ������ɤ��������
������ɤ��������![]() �����Ϥ�̵���ԻԤǤ�����ߤ��Ǥ�����������Ǥ��롣�ʤ����⥳���ȤˤϤʤ뤬���������϶����ؤ�Ʊ���˷��Ƥ���ȡ����ʤ��
�����Ϥ�̵���ԻԤǤ�����ߤ��Ǥ�����������Ǥ��롣�ʤ����⥳���ȤˤϤʤ뤬���������϶����ؤ�Ʊ���˷��Ƥ���ȡ����ʤ��![]() �����Ϥ�����Ǥ��롣
�����Ϥ�����Ǥ��롣
������ǽ���ͥ륮���ؤ�������ϡ�������ȯ�Ž����ǽ���夲��ǽ�ϡ�
������ȯ�Ž��![]() ���Ϥ����Τޤ�
���Ϥ����Τޤ�![]() �Ѹ��Ϥˤʤ������仺�֥Х������ե����פ��Ȥ߹�碌�ƿ�����ȯ�����롣�ޤ����ʳؾ����Ǥ�Ǹ�ΰ첡����
�Ѹ��Ϥˤʤ������仺�֥Х������ե����פ��Ȥ߹�碌�ƿ�����ȯ�����롣�ޤ����ʳؾ����Ǥ�Ǹ�ΰ첡����![]() ���Ϥ�ɬ�פʾ��̤⤢��Τǡ����Ȱ첡�����ߤ������Ϻ��Ѥ�Ƥ��������
���Ϥ�ɬ�פʾ��̤⤢��Τǡ����Ȱ첡�����ߤ������Ϻ��Ѥ�Ƥ��������
���쥤�ޥ�1��(Ωˡ��)��ͭ�����ġ���˷���������ζ�������Ū�ˤ��Ƥ��롣
�ĥ��1���ܤϷ�����2��3���ܤϳ���˴ؤ��륹���롣
�����ΰ�ư��������γ����ѥ�����ʤɤȹ�碌�����ְ�ư��¿���ʤ꤬���������ӥ�����Ʊ��3������ǰ�ư����ΤǷ䤬�ʤ���
��ά����/ɾ��/ʸ������Ƴ�� �Ρ֥��쥤�ޥ�1��(Ωˡ��)�פ⻲�ȡ�
���ѥܡ��ʥ����ѥ����ϡ�������˥åȤ�����®�٤����ǽ�ϡ�
����ɮ�Ԥ�
�뾢Ƭ�ϡ��ԻԤ��ɱ��Ϥ����ǽ�ϡ�
����ɮ�Ԥ�
���饹�����ϡ������������̤����ԻԹ��������ʤ˳ڤˤ��붯����ǽ�ϡ�
�ܡ��ʥ���ͭ���ϰϤϾ����ԻԤ��Կ�����10���������ʤΤǡ����κǴ����ԻԤ��ɸ����褦�����Ť��餳�β��ä��������Τ�ߡ�
�ϡ��å����������Х������ס��������ϡ����֥�ҥ�����ʸ����![]() ���Ԥ˾�����ȸ��̤��Ф�Ȥ���������ǽ�ϡ�
���Ԥ˾�����ȸ��̤��Ф�Ȥ���������ǽ�ϡ�
�ɤ���⳰������θ��̤Ǥ��ꡢ¾ʸ���Ȥγ����ͭ���ˤ��뤳�Ȥ���ǽ�ˤʤ롣�ȤϤ���Ʊ���ݥ���Ȥ���ʿ�ϰռ����ƥ���ȥ����뤷�Ť餤���ᡢ���ޤ���̥�Ϥ��ʤ���
������ϡ�����������ʸ����![]() ���Ԥ˾�����ȸ��̤��Ф�Ȥ���������ǽ�ϡ�
���Ԥ˾�����ȸ��̤��Ф�Ȥ���������ǽ�ϡ�
���ܤ���ʸ��Ūʸ����������������Ϥ��ɤ��������Τ����ԻԤ�ȿ����ɤ��Ȥ�ƻ���ͤ����롣��Ԥξ�硢��������ʸ���ˤ�![]() ���Ĥ��ɸ��Ǥ��ʤ��Τ������ʿ���ʤ���Фʤ�ʤ�����äơ����������˺����������饹�������ä����֥�ҥ�����֤���
���Ĥ��ɸ��Ǥ��ʤ��Τ������ʿ���ʤ���Фʤ�ʤ�����äơ����������˺����������饹�������ä����֥�ҥ�����֤���![]() ��Ʈ�ϥ֡����� �� Ũ�ԻԤ����Τ�����������ش������ä��ӥ��������ɸ������������㲼�ɻ� �� ��ʿ���Ũ���
��Ʈ�ϥ֡����� �� Ũ�ԻԤ����Τ�����������ش������ä��ӥ��������ɸ������������㲼�ɻ� �� ��ʿ���Ũ���![]() ���Ԥ˥��֥�ҥ���ɸ����Ƥ�������Ų��פȤ���ή�줬����Ū�����ä���꤬
���Ԥ˥��֥�ҥ���ɸ����Ƥ�������Ų��פȤ���ή�줬����Ū�����ä���꤬![]() ������塢�����餬
������塢�����餬![]() �Ź�����ʤɤ����������Ϥ�����䤹������
�Ź�����ʤɤ����������Ϥ�����䤹������